公益法人会計の勘どころ(正)に続けて、収支計算ベースと損益計算ベースの収支計算を両立させる仕組みなどについて説明します。
公益法人が作成しなければならない決算書は、貸借対照表と正味財産計算書です。
企業会計では、正味財産の増減を損益取引に係る「損益計算書」と正味財産の増減に係る「株主資本等変動計算書」の2表に分けて表示しますが、それぞれは公益法人会計の「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に相当し、公益法人会計ではこれを一つの「正味財産増減計算書」として表示します。したがって、公益法人会計の簿記の仕組み(2)に図示した「公益法人会計」(新基準)の取引8要素に従って複式簿記を実行すれば自ずと「正味財産増減計算書」ができます。
公益法人が作成しなければならない「収支予算書」とは、この正味財産増減の予算書です(認定規則30条1項、6項)。したがって、「収支」といっても「収益」と「費用」からなっており、「収支」を示すものではありません。これが損益計算ベースの収支計算書の大きな特徴です。
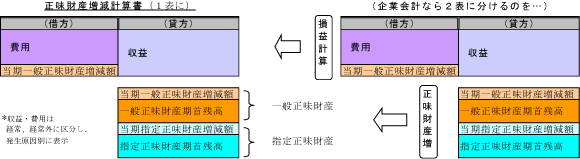
平成16年基準から「正味財産増減計算書」がフロー式に統一され公益法人会計は損益法になっていますが、移行するまでは収支ベースでの「収支予算書」とこれに対応した「収支計算書」の作成が求められています。これにどう対応したらいいですか。
公益法人会計が損益法になったことにより損益計算ベースの正味財産増減計算書は自ずと作成できますが、これには固定資産の取得支出や借入金収入など正味財産の増減を伴わない交換取引による収支が含まれていません。したがって、これだけでは「すべての収入及び支出」(H17.3.23内部管理事項申合せ)は把握できません。予算統制が徹底しません。
これに対処する方法はいくつかあります。
(ⅰ) 一つは、地方公営企業会計が採っている方法で収支を収益的収支と資本的収支に2分し、収益的収支は損益ベースの「収益」「費用」をもってあて、交換取引その他の損益外取引収支をもって資本的収支とする方法です。この方法では、収益的収支は損益計算ベースのものとなります。
(ⅱ) 一つは、損益法による会計処理と平行して、従来の収支計算体系を維持する方法です。次のようにします。
(ア)商品100万円を現金で仕入
| (借方)事業費(費用) | 100万円 | (貸方)現 金(資産) | 100万円 |
| (借方)事業費支出(収支) | 100万円 | (貸方)現 金(資金) | 100万円 |
(イ)商品140万円を現金で売上
| (借方)現 金(資産) | 140万円 | (貸方)事業収益(収益) | 140万円 |
| (借方)現 金(資金) | 140万円 | (貸方)事業収入(収支) | 140万円 |
(ウ)備品40万円を現金で購入
| (借方)備 品(資産) | 40万円 | (貸方)現 金(資産) | 40万円 |
| (借方)備品購入支出(収支) | 40万円 | (貸方)現 金(資金) | 40万円 |
| (借方)備 品(資産) | 40万円 | (貸方)備品購入額(正味) | 40万円 |
| または | |||
| (借方)備 品(資産) | 40万円 | (貸方)現 金(資産) | 40万円 |
| (借方)備品購入支出(収支) | 40万円 | (貸方)備品購入額(正味) | 40万円 |
このうち青色の仕訳が損益法による会計仕訳であり、その他がストック式の収支計算仕訳です。従来のストック式に比べてもすべてが「1取引2仕訳」となっており、(ウ)に至っては「1取引3仕訳」です。完全な二重仕訳です。
(ⅲ) そこで複式簿記の体系に沿って、会計仕訳だけで損益計算ベースと収支計算ベースの収支計算書を同時に作る仕組みはないかですが、あります。それが地方公会計の基準モデルが示している「資金収支計算書」の作り方です。これが次に説明する「キャッシュフロー式」です。
(ⅳ) その他帳簿組織を通さない誘導法はいろいろありますが省略します。
(収支計算書の損益法への対応は)の(ⅱ)の会計仕訳(青色)の現金(資金)勘定を収支事由(予算科目)別に下位区分し、資金収支については、この下位勘定をもって仕訳する。それだけです。そうするとすべての資金収支が収支事由別に各資金勘定に蓄積されるので、これを集めるといつでも予算科目に対応した収支計算ベースの収支計算書が得られます。収支が貸借逆になりますが、内容は従来の「収支計算書」と同じです。
具体的には次のようにします。
(ア)商品100万円を現金で仕入
| (借方)事業費(費用) | 100万円 | (貸方)事業費支出(収支) | 100万円 |
(イ)商品140万円を現金で売上
| (借方)事業収入(収支) | 140万円 | (貸方)事業収益(収益) | 140万円 |
(ウ)備品40万円を現金で購入
| (借方)備 品(資産) | 40万円 | (貸方)備品購入支出(収支) | 40万円 |
(収支計算書の損益法への対応は)の(ⅱ)の会計仕訳と違うのは、アンダーラインの科目だけです。
各勘定の流れは次のようになり、結局、「収支」は貸借対照表に、「一般正味財産」は「正味財産増減計算書」に集約されて、損益計算ベースと収支計算ベースの計算書が同時に得られるようになります。
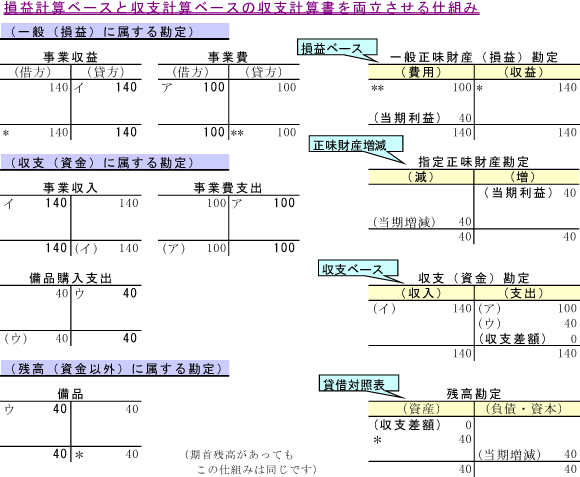
(1) ストック式の収支計算書の本質
ストック式の収支計算書は、次のようになっています。つまり、ストック式の収支計算書は、財産法による正味財産の増減計算書の一部で、資産の一部である資金の増減計算書ではありません。これに対しキャッシュフロー式の「収支」は資産である資金そのものの増減ですから、その増加である「収入」は借方となりますが、ストック式は正味財産の増減を表していますからその増加(収入)は貸方になります。「収支」が貸借逆になっているのはこういう本質的違いからです。結局、ストック式の収支勘定は正味財産勘定であるのに対し、キャッシュフロー式の収支勘定は貸借対照表勘定であり、ストック式の収支計算書は、正味財産増減計算書としての収支計算書です。しかし、損益法では正味財産の増減計算は「収益」「費用」等の勘定を通じて行われますので、収支勘定を通じて重ねてこれを行う必要はないわけです。
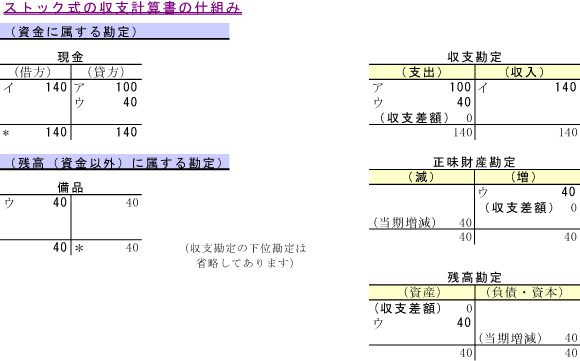
(2) 財産法から損益法の転換の隠れた事情
ストック式の正味財産計算書は、「資産及び負債の各科目別に増加額及び減少額」を表すものです(旧基準第5・2)。しかし、そうであれば複式簿記の必要はなく、すべての資産・負債の増減を単式で記録し、それを資産・負債の科目別に表示すれば足ります。
つまり、「資金」その他の資産・負債の増減はその勘定自体が持っていますから、複式簿記の形をとっても、相手勘定には本来記録すべき情報がなく空っぽです。いわば空き部屋です。ストック式は、これを利用しているわけです。すなわちこの空き部屋に資産・負債の増減を収支事由別に記録し、正味財産計算書を導いているわけです。したがって、ストック式の正味財産計算書は、実は、資産・負債の科目別にではなく、収支事由別になっています。これがストック式の収支計算の真のねらいでしょう。
しかし、損益法になると、この方法は取れません。というのは、損益法では、「資金」の相手勘定には「収益」「費用」「資産」「負債」「資本」のいずれかの勘定で必ず反対記入されるので、もはや転用できる空き部屋はありません。損益法では「収益」「費用」勘定等により発生原因別は明らかにされるので、その必要もありません。財産法から損益法の転換にはこういう隠れた事情もあります。
旧基準では短期債権・債務まで「資金」に含めることが推奨されてきましたが、キャッシュフロー式でも「資金」の範囲をそこまで拡張することはできますか。「資金」の範囲はどうするのがいいですか。
(1) まず、資金の範囲を拡張できるかですが、できます。補助勘定を付けるだけです。
(2) 次に、短期債権・債務まで含めるべきかどうかですが、旧基準が「資金」に短期債権・債務まで含めていたのは、それが収支ベースで損益ベースとずれていたからです。それを近づける工夫の一つがこれです。しかし、損益状況が一般正味財産の増減として別途求められるようになった16年基準以後の「収支計算書」ではこれを考慮する必要はありません。むしろ「資金」の範囲を予算の対象と同じ現金及び現金同等物に限定し、同一処理が可能にした方が合理的です。