前回に続けて公益法人会計の実践的課題やわかりにくいところなどを説明します。
- わずらわしい仕訳からの解放
- 「資金」の範囲を拡げても仕訳を省力化できますか
- 予算は何を統制しているのですか
- 予算差引簿に支出負担行為額欄を設けると
- 「収益的収支」と「資本的収支」に2分する地方公営企業会計方式とは
- 「当期収支差額」を赤字・黒字というのは二重の意味で正しくありません
- 減価償却等により内部留保した資金はどこにあるの
- 減価償却引当資産の設定と減価償却は
- 資金収支の対象となる「現金預金」とは
- ストック式の「正味財産増減勘定」は「非資金増減勘定」です
- 資金間取引は仕訳しなくていいのでしょうか
- ストック式でいう「連結環」とは
公益法人の取引は、ほとんどが資金収支であるため、同じことを二重、三重に記録することとなっています。しかし、この重複を体系的に排除し、効率化することができます。
すなわち、予算科目と会計科目を対応させ、資金の範囲を予算と同じにすれば、予算差引がすなわち収支計算ベースの収支計算となります。そして、予算差引簿等を補助簿とみなして、これから合計仕訳することでほとんどの仕訳が不要となります。減価償却等資金収支を伴わない取引だけを個別に仕訳すれば完成です。これで必要な財務諸表も収支計算書も作成できます。
これらに関しては、「これならわかる新地方公会計」第3章2、4をご覧ください。
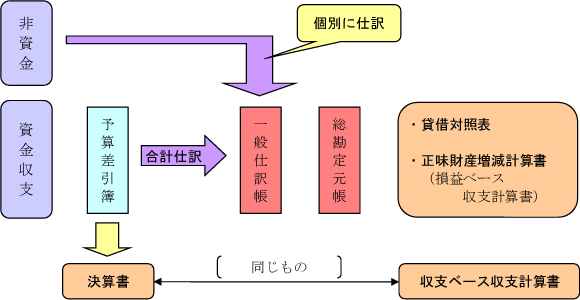
できます。(わずらわしい仕訳からの解放)で作成した収支ベースの収支計算書に、期末に個別仕訳で追加した未収金・未払金に係る収支を加えるだけです。月次処理の場合は、翌月の回収・支払と重複しないように未収金・未払金を一旦ゼロに戻しておきましょう。
なお、予算差引簿に支出負担行為額欄(収入については調定額欄。以下同じ。)がある場合は、それが拡張した「資金」の収支額ですからそれで仕訳すれば追加仕訳も不要です。
契約締結と同時に代金支払債務が発生します。お金がないからとか、要らなくなったからとかいっても一方的には破棄はできません。したがって、予算準拠主義を徹底するなら、現金の収支ではなく、その原因となる行為を統制しなければなりません。支出負担行為・収入の調定がこれです。官庁会計は、すべての金銭の給付を目的とする債権・債務(「財務資源」といいます。)を対象に統制をしています。公益法人については、予算の拘束力に関する法律の規定がなく、予算準拠主義をどこまで貫くかは各法人の自治に委ねられています。しかし、公益法人が作成しなければならない「収支予算書」はすべての者の閲覧に供されており(認定法21条)、企業の予算書とは違います。単なる見積書ではなく、予算書です。拘束力があります。
次のようなメリットがあります。
- 会計の仕組みがすっきり、しっかりします。上半分が支出負担行為額(収入については調定額)による発生ベースの財務諸表の世界、下半分が支出額(収入については収入額)による現金ベースの決算の世界です。
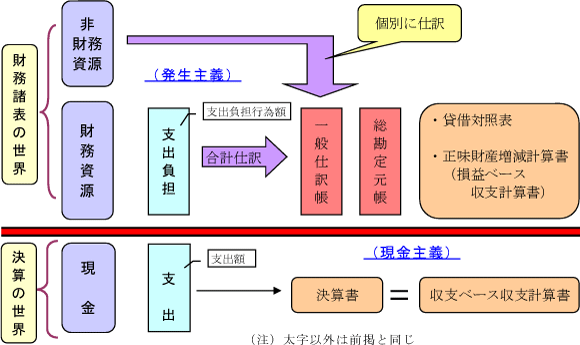
- 財務資源には長期、短期すべての金銭債権・金銭債務が含まれているので個別仕訳は年度末の減価償却費等極限られたものになり、更に省力化できます。
- 月次では財務資源を対象とする支出負担行為情報も財務会計情報も同じですから、どちらでも同じように有益な情報が得られるようになります。
- そもそも仕訳に必要な未収金・未払金情報は得意先元帳等で把握しておかないと得らません。このタイプの予算差引簿はこの機能を担っています。したがって、これがあればそれが省略できます。
- そして、予算差引簿から発生ベースと現金ベースの二つの情報が得られるので、合理的な会計処理の仕組みを体系的に自在に設計できるという大きなメリットがあります。
公益法人会計の「資金」「非資金」の区分は便宜的なものです。例えば、長期割賦払いで収益が発生した場合、それは「非資金」ですから収支計算と損益計算が大きくズレます。こうした矛盾が起きないように体系化したのが地方公営企業会計方式です。
すなわち、すべての取引は損益取引か損益外取引(交換取引と資本取引)かですから前者を「収益的収支」、後者を「資本的収支」として先の矛盾を体系的に解消しています。「収益的収支」とは「収益」「費用」のことであり、完全に「損益計算書」と一致します。表示も「○○収入」「○○支出」ではなく「○○収益」「○○費」となっており、現金の収支を伴わない減価償却費等も含みます。公益法人化後に作成が義務付けられている「収支予算書」はこれです。地方公営企業会計は予算からこの方式を採っています。なお、地方公営企業では、減価償却費の計上までは予算の制約は受けないものとしています。
財産法と損益法は表裏の関係ですからどちらで計算しても結果は同じになります。しかし、これには二つの条件があります。
一つは測定の対象がすべての資産・負債であることです。損益法は、財産法がすべての資産・負債を対象とするときだけ一致します。収支計算ベースの「当期収支差額」は、資産・負債の一部である「資金」の増減を対照とするものですから、経営の赤字・黒字は示しません。キャッシュフロー式収支計算書の具体的な作り方の例では、(ア)事業費用100万円(現金)、(イ)事業収益140万円(現金)で実際40万円“もうかっている”のに(ウ)備品購入で現金40万円を支出したために資金の収支差額は“ゼロ”になっています。
もう一つの条件は、減価償却や引当金の設定その他資金の収支を伴わない財産の増減を財産の増減として認識することです。ストック式ではこれらは「正味財産増減勘定」に計上し、「収支勘定」には計上しませんからこの点でもズレが生じます。
前項の取引例(ア~ウ)に、更に(エ)減価償却費40万円がかかったとします。そうすると、備品購入前の収支差額は同じく40万円(140万円-100万円)ですが、損益は0円(140万円-(100万円+40万円))です。もしこの減価償却費が資金流出を伴う普通の費用であれば、備品購入の40万円の余裕資金は生じません。これが内部留保とか自己金融といわれるものですが、余裕資金が発生しても、使えばなくなります。この例では、備品に姿を変えており、資金はどこを探してもありません。あるいは、その40万円で借金を返済する場合もあります。その場合は余裕資金は負債の減少に顕現しているわけです。内部留保といってもそれが資金の形で在るという意味では決してありません。
また、これを自己金融というのは、備品を買うには資金が必要ですが、それを借入れでなく、自己資金で調達できたという意味です。金利の有無が違います。
- 減価償却は次のような仕訳になります。
(借方)減価償却費(費用) (貸方)○○資産(資産)…(直接法)
つまり資産の目減り分の費用計上です。
- これに対し、減価償却引当資産の設定は、次のようになります。
(借方)減価償却引当資産(資産) (貸方)現金預金(資産)
これは支払準備のための資産から資産への振替えに過ぎません。
- したがって、減価償却とその引当資産の設定は違います。減価償却は強制ですが、引当資産の設定は任意です。強制されていません。
- これらは退職給付引当金の設定等についても同様です。
公益法人会計では同じ現金預金が流動資産の「現金預金」になったり、固定資産の特定資産等になったりしますが、資金収支計算の対象となる現金預金とは何をいうのですか。
収支計算の対象とする資金に属する現金預金にはこれに準ずるものも含みますが、基本財産又は特定資産を構成する現金預金は含みません。つまり流動資産の「現金預金」です。ただし、例えば、退職給付引当資産を設定した場合は他方で「現金預金」をその資産取得のために支出することになり、同資産を取り崩せば「現金預金」がその取崩し収入によって増えるという関係ですのでご注意ください(内部管理事項申合せ・別表(投資活動収支の部))。
なお、この「現金預金」を運用資産としての現金預金だといわれることがありますが、基本財産以外を運用資産だとすると、特定資産の現金預金を含むこととなり、現在では、適切な表現ではありません。
ストック式は、「資金」と「非資金」に2分して、財産の増減を測定します。したがって、正味財産の増減であっても、「資金」の増減は「収支勘定」に、「非資金」の増減は「正味財産増減勘定」に仕訳します。つまり、「正味財産増減勘定」はすべての正味財産の増減を仕訳する勘定ではなく、「非資金」の増減を仕訳する勘定です。
現金売上など正味財産の増減があっても「正味財産増減勘定」に仕訳しないのはこのためです。また、備品の購入(収支計算書の損益法への対応はの(ウ))など「一取引二仕訳」といわれるものは、「資金」「非資金」それぞれの増減があったわけですから会計的には当然の仕訳であり、「一取引二仕訳」というより「二取引二仕訳」です。
正確には「収支勘定」を相手方とする収支仕訳は不要ということです。未収金を回収して現金が増えているのに、何も仕訳しなければ未収金は永遠に減りませんし、現金残高も一致しません。取引どおりに次のように仕訳します。
(借方)現金(資金)×××× (貸方)未収金(資金)××××
期末の資産・負債=期首在り高+期中増減額ですが、企業の財務諸表にはこの期中増減額を直接表現するものはありません。資産・負債の科目別増減を表すストック式の正味財産計算書はこの期中増減額を表すものです。「連結環」としての機能とは、このことです。つまり、正味財産計算書は期首と期末の資産・負債をつなぐ環だという意味です。資産・負債が貸借対照表に掲載され、それが翌期の活動資源として繰越されていくという意味で貸借対照表を「連結環」というのとは意味が違います。