公益目的事業財産をめぐっては、二つの注意が必要です。一つはこれと認定基準との関係であり、もう一つは公益目的保有財産その他の財産との関係です。
なお、一般法人法は、今後、法人法と略称することにします。
- 公益目的事業財産とは何ですか
- 認定後繰入表示財産とは
- 公益目的事業財産を定めている趣旨は何ですか
- 公益目的保有財産、公益目的取得財産残額との関係は
- 公益目的財産額、公益目的財産残額とは
- 公益目的事業財産は認定基準とどう関係するのですか
- 公益目的事業財産の範囲を調整できるのは公益目的保有財産だけですか
- 会費等の取扱いはどうなっていますか
- 公益目的事業しか行わない法人の管理費はどこから調達すればいいですか
公益目的事業財産とは公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない、次の8つの財産をいいます(認定法18)。モノ(公益目的保有財産)と資金(公益目的保有財産以外の財産)とがあります。
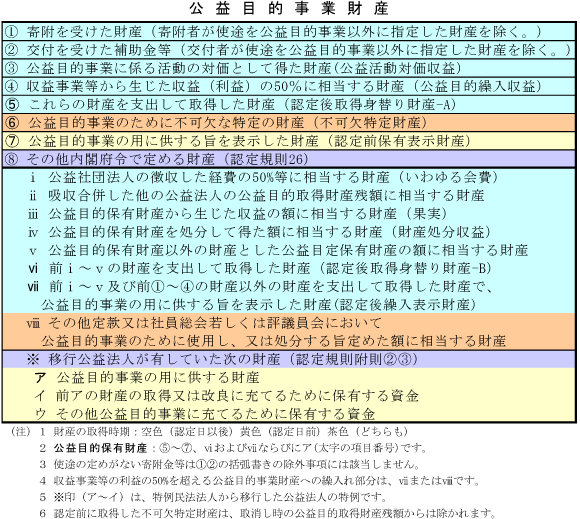
収益事業等の資金で取得した財産で、法人の判断で表示することにより公益目的保有財産とした財産ですが、認定前保有表示財産と区別するための便宜的名辞です。財産目録、貸借対照表またはその附属明細書において財産の勘定科目を他の財産の勘定科目と区分して表示します。これらは継続して公益目的事業の用に供するために保有している財産に限ります(認定規則25、26七)。なお、定款・社員総会・評議員会によるその他の繰入財産(認定規則26八)には、表示その他これらの制約はありません。
- これまでは、公益目的事業、収益事業等及び法人管理業務の区別を意識することなく、それぞれの成果を他の財源に充当することができましたが、これからはそれぞれの財産、収益を区別し、それぞれごとに管理しなければならないということです。
公益目的事業財産は、公益目的事業以外の事業その他の業務・活動には使用できませんので、例えば、公益目的保有財産の果実を法人の管理費に充てることはできませんし(認定規則26三)、収益事業等収益の50%相当額は公益目的事業のために使用し、処分しなければなりません(認定法18四)。
- 公益目的事業のための財産は、最後までそのために使用することが求められています。公益認定が取消された場合等には、公益目的事業財産の未使用残である公益目的取得財産残高(認定法30②、認定規則49)に相当する財産は、取消等から1ヶ月以内に類似の事業を目的とする公益法人等に贈与しなければなりません(認定法5十七、30①)。
一般法人が解散した場合、残余財産の帰属は、定款等の定めるところにより法人の判断に委ねられています(法人法239)が、このうち公益目的取得財産残高については、この制限を受けます。各事業年度においても公益目的取得財産残高に準じてその額が管理されます(認定規則48)。
- 公益目的事業財産は、(公益目的保有財産+資金(収益))ですが、公益目的事業のために費消されますからそれを合計しても現在高にはなりません。
- 各事業年度の末日における公益目的事業財産の未使用残である公益目的取得財産残額は、モノと資金に分けて、次のように捉えられます(認定規則48、49、同附則⑤、⑥、FAQⅤ-4-③)。
|
公益目的取得財産残額=当期公益目的増減差額+当期末公益目的保有財産の額 |
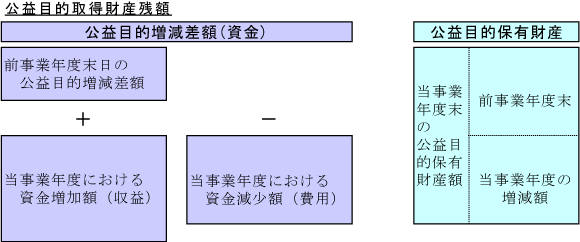
特例民法法人が一般法人に移行する場合には、移行時における残余財産に相当する公益目的財産額を公益の目的のために支出してゼロにするための公益目的支出計画を立てますが、公益目的財産額及び公益目的財産残額は、この公益目的支出計画上の概念で(整備法119)、公益法人とは無縁のものです。
また、公益目的事業財産は公益目的事業のために使わなければなりませんが、公益目的財産額は、それに限らず、移行法人が移行後も引き続き行う公益の目的(旧公益目的事業)のためにも使われます(整備法119②一)。公益目的財産額は移行時におけるその未使用残額であり、公益目的財産残額はそれから公益の目的のための支出の額を控除した未使用残額です(整備規則14、16)。どちらも旧公益概念に対応の公益目的取得財産残額です。
公益目的事業財産の範囲は、法人の判断で変わります。例えば、ある財産を表示して公益目的保有財産にする・しないです。この調整の仕方で認定基準が次のような影響を受け、認定基準がクリヤーできたり、できなかったりする可能性があります。
- 公益目的事業の収益サイドに影響します。したがって、収支相償基準に影響します。
例えば、公益目的保有財産の処分収益や果実は公益目的事業の収益となりますので、ある財産を公益目的保有財産とするか・しないかによって収支相償の状況が変わります。 - 公益目的事業の費用サイドにも影響します。したがって、収支相償や公益目的事業比率に影響します。
例えば、ある減価償却資産を公益目的保有財産とすると、その減価償却費や修繕費等は公益目的事業の費用となりますが、そうでないとなりません。 - 遊休財産額の保有制限に影響します。これには二つの面があります。
一つは、この上限額です。これはその年度の公益目的事業の実施費用の額ですが、これがⅱの影響を受けます。もう一つは、遊休財産額です。遊休財産額の算定上公益目的保有財産は控除項目ですからその影響を受けます。
公益目的保有財産とは限りません。寄附金(公益目的事業財産の表の①)、いわゆる会費(ⅰ)、50%超の収益事業等からの繰入(ⅶ、ⅷ)など調整可能な収益項目があります。
法人がどういう者を会員、準会員、特別会員とし、それらの者から会費を徴収するかどうかは法人の任意です。したがって、一般(公益)社団法人の社員だから当然に会費支払義務があるわけではありませんが、社団法人の場合には、定款で定めるところにより、社員から経費を徴収することができます(法人法27)。これに基づき徴収する経費がいわゆる会費です(認定規則26一、FAQⅥ-1-④)。それ以外の会費等とは区別されます。
- いわゆる会費
徴収に当たり使途が定められていなければその50%が、定められていればそれにより公益目的事業に使用すべきものと定められている部分が公益目的事業財産(収益)となります。この使途は、割合をもって定めることができ、内部規定で定めることもできます(ガイドラインⅠ-17)。 - いわゆる賛助会費等
いわゆる会費(ⅰ)以外の公益社団法人・公益財団法人が会員等から徴収する会費、賛助会費等は、基本的に寄附金の扱いとなります(認定法18一、FAQⅥ-1-①)。したがって、これらの賛助会費等は、その徴収に当り使途が定められていなければその全額が、定められていればそれにより公益目的事業に使用すべきものと定められている部分が公益目的事業財産(収益)となります。ただし、社団法人において、会員の中から選挙で選ばれた者のみを社員とする場合の社員以外の会員が支払う会費については、いわゆる会費(ⅰ)に準じて取り扱われます。返還を予定しない入会金についても同様です(ガイドラインⅠ-17)。